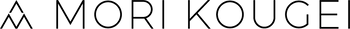漆について
漆(うるし)は、漆の木から採取される樹液で、数千年にわたり日本の食器や工芸品などに使用されてきた、自然由来の素材です。
漆塗りは、その耐久性、耐水性、そして美しい光沢で知られ、古来から食器や家具、芸術品の仕上げに使われ、長い歴史を通じて磨かれてきました。
私たちは漆の持つ美しさとツキ板との融合で新たに生まれる可能性を追求し、毎日の食卓を一層特別なものに変えることを目指しています。
漆製品を生活に取り入れる―― そうすることで、和の美しさだけでなく、日本の伝統とモダニズムを組み合わせたPLATEで日々の暮らしを豊かにすることができます。


[歴史的背景]
漆の使用は、約9000年前、つまり日本で言うと縄文時代にまで遡ります。その後、平安時代(8世紀末~12世紀末)には漆器が貴族社会で広く用いられるようになり、漆工芸は大きく発展しました。
特に、室町時代(1336~1573)から江戸時代(1603~1868)にかけて、漆器は日常生活の中で広く使われるようになり、多様な技法が生み出されました。加賀蒔絵や輪島塗など、地域ごとに特色ある漆工芸が育まれています。
近代に入り、漆は伝統工芸品だけでなく、現代の家具やインテリア、アートの分野でも使用されるようになりました。

[漆の性能とメリット]
漆は天然の樹液でありながら、固化すると非常に硬い塗膜を形成します。この塗膜は、耐水性、耐熱性、さらには抗菌性を兼ね備えており、日々の使用においてもその美しさを長く保ちます。
直接食材を盛り付けることができ、水洗いも可能。日常のお手入れも簡単です。


・自然由来であること
漆は天然の樹液なので、当然ながら化学物質は一切含みません。環境にやさしい自然由来のサステナブルな素材です。
・耐久性
漆は固化すると非常に硬い塗膜を形成し、水や化学物質、熱に対する抜群の耐性を持ちます。長期間にわたって製品の美しさと機能性を保つことができます。
・抗菌性
漆には自然な抗菌作用があり、食器や家具など、衛生が重視される製品に適しています。これはウレタン塗料にはない漆の大きな特徴です。
・独特の光沢と質感
漆を使用した製品は、深みのある光沢と温かみのある質感を持ちます。この漆特有の美しさは、ウレタン塗料では表現できません。
・修復可能性
漆は傷がついても修復することができるのも特徴。長い歴史を通じて技術が継承されています。
[ 自然の美しさを守る]
天然の樹液である漆。その採取から加工に至るまで「漆を一滴も無駄にしてはならない」をモットーに自然や環境への配慮を考え、次世代につなぐ活動も行っている、京都の『堤淺吉漆店』とコラボレーションすることを決めました。

最高品質の漆を選び、それを丁寧にPLATEに施しました。漆の深みのある光沢は、ツキ板の繊細な木目を際立たせ、自然の美しさを最大限に引き出しています。

[ 漆製品の魅力]
漆で仕上げた器は独特の風合いを持ち、使い込むほどに個性を増していきます。この時間とともに見られる経年変化も漆ならではの楽しみの一つ。これは、他の素材にはなかなか見られない特性です。
[堤淺吉漆店について]
明治42年(1909年)の創業以来、漆を精製する堤淺吉漆店。
10年~15年の成木から牛乳瓶1本分(200cc)ほどしか採取出来ない、貴重な自然の恵みである漆。「漆を一滴も無駄にしてはならない」という想いは、1世紀以上が経った現在でも社訓として受け継がれています。
堤淺吉漆店は、漆器、茶道具、仏壇、仏具、国宝・重要文化財建造物修復、一般社寺建造物の修復をはじめ、西陣織、和洋家具、竹工芸、雅楽器など、様々な分野で幅広く漆を提供。それぞれの分野や産地、使用される条件や環境、職人さんの好みなどで使用する漆は異なるが、乾きや粘度、色合いや艶の調整など、多種多様なニーズに応え、精製しています。
時代とともに精製技術や設備は進歩し、生産量も増え、スピードも速くなったが、「漆を一滴も無駄にしてはならない」という精神は変わりません。
漆を次世代につないでいくため、京都の郊外に漆の木を植える活動など、裾野を広げるための運動にも力を注いでいます。「木」に携わっている人たちにも焦点を当て、漆を使った完成品だけでなく「素材」の魅力を発信しています。
その一環として2024年4月にフラッグシップショップ「Und.」をオープン。漆芸専門ショップ、イベントやワークショップができるスペースや漆芸工房も併設。
また、サーフボード、スケートボード、自転車フレームなど、多様な漆プロダクトの制作も手掛けています。
https://www.tsutsumi-urushi.com/urushix





[ツキ板と漆が生み出す新しい日本の現代工芸]
MORI KOUGEIは、美しい木目を持つツキ板をそのまま貼るだけでなく、木目で模様を構成することでさまざまな意匠を提案してきました。
これまで培った技術と経験を活かし誕生させたPLATEは、ホワイトシカモアの波紋模様を活かすことにこだわりました。

そして、日々の食卓で使用していただくことを考え、食材を盛り付けることはもちろん、日常的なお手入れのことを考慮しつつ、木目を美しく見せるための適正な塗装を選びました。その一つが、トップコートとして最も性能が高く、文化的価値の高い『漆』でした。
「100%天然素材で仕上げたい」という想いもあり、漆を使うことははじめから考えていましたが、木目が消えてしまわないだろうか…という懸念があったのも事実です。
木目を活かすことができる漆仕上げの製品を模索する中で、幸運なことに堤さんとのご縁がありました。
互いに試行錯誤を重ね、木目模様の美しさが引き立つプロダクトを作ることが可能になったのです。漆を施すことで、ホワイトシカモアの波紋模様の美しさが一層際立たせることができました。
漆の特徴として、時間とともに透け具合や色味が変わってゆく経年変化が魅力の一つです。

その繊細な美しさと精緻な技術で世界中から高く評価される日本の伝統工芸。
ツキ板の「貼り」の技術を活かし、仕上げに漆を施したPLATEは、伝統的な技法を踏襲した新しい日本の現代工芸の粋を目指しています。
長い歴史を持つ素材を現代のライフスタイルに合わせて再解釈し、新しい価値を創造するMORI KOUGEIは、日本の伝統ある素材を現代に生かすことで、工芸品の未来に向けた新たな一歩を踏み出しました。
今後、PLATEだけでなく、日本が誇る漆を使った商品開発を行っていきたいと考えています。